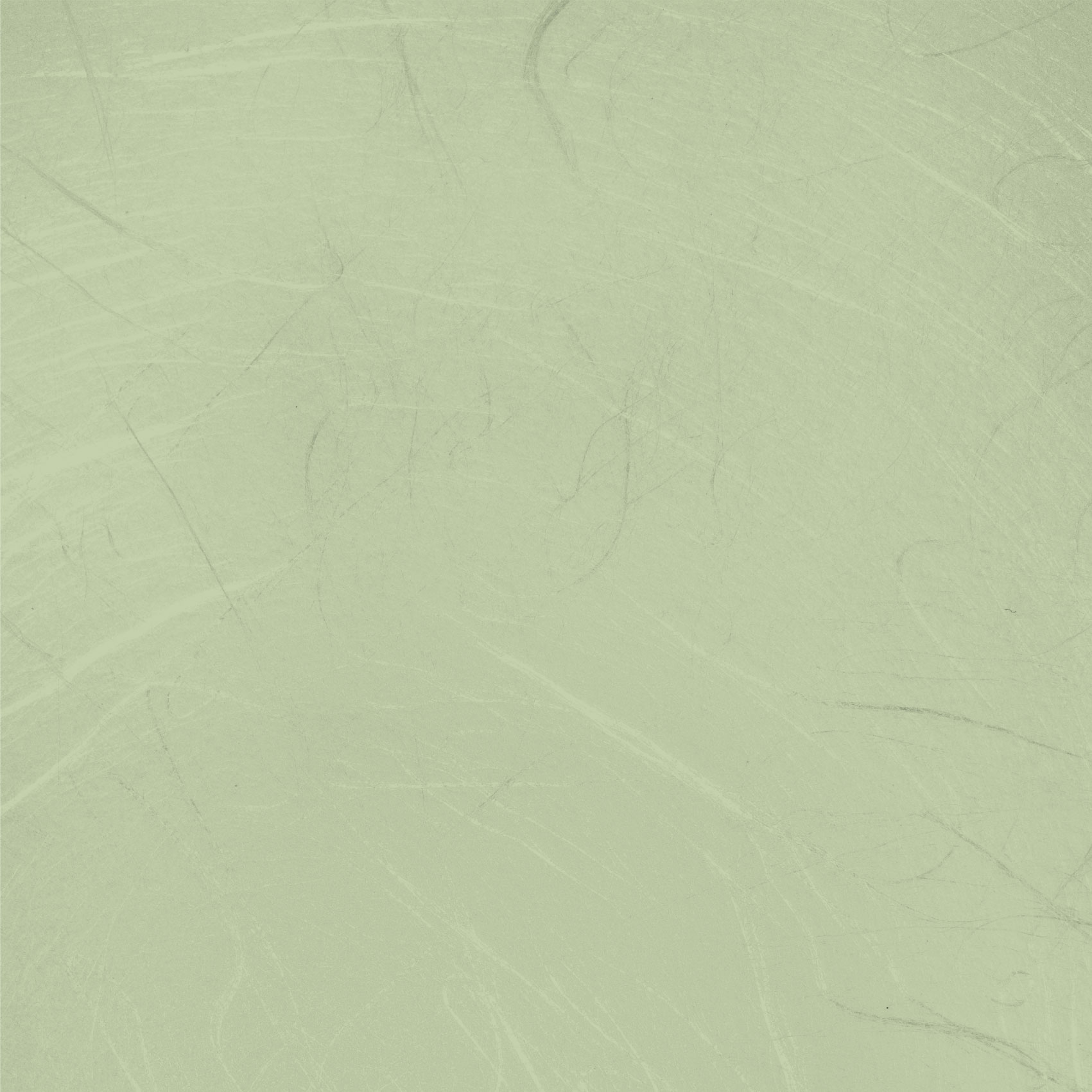永代供養とは?後継者不要のお墓の種類・費用・選び方を完全ガイド
投稿日:2025年7月1日

目次
- 永代供養とは何か?
- 永代使用料との違い
- 永代供養の種類と特徴
- 合祀型(ごうし型)
- 個別型・集合型
- 個別型の特徴
- 集合型の特徴
- その他の供養スタイル(樹木葬・納骨堂など)
- 永代供養にかかる費用と相場
- 費用相場の目安
- 費用の内訳
- 年間管理料について
- 永代供養のメリット・デメリット
- 永代供養の主なメリット
- 永代供養の主なデメリット
- 永代供養はこんな人におすすめ
- 永代供養のお墓を選ぶポイント
- 納骨する遺骨の数を確認
- 埋葬方法と合祀までの期間
- 寺院の宗派・供養の方法
- 費用と維持費の有無
- 立地と設備の利便性
- 永代供養の具体的な手続き
- 既存のお墓がある場合(改葬・墓じまい)
- 新規に利用する場合
- 生前契約について
- よくある質問(FAQ)
- Q1. 永代供養と納骨堂の違いは?
- Q2. 永代供養にお布施は必要ですか?
- Q3. 永代供養料を払う時のマナーはありますか?
- Q4. 永代供養に宗派は関係ありますか?
- Q5. 浄土真宗では永代供養できないって本当ですか?
- Q6. 子どもがいても永代供養を選んでいいのでしょうか?
- Q7. 永代供養墓でもお墓参りはできますか?
- まとめ
お墓の後継ぎがいなくて悩んでいませんか?近年、そんな不安を解消できる「永代供養」が注目されています。実際、全国お墓の実態調査によると、購入検討者の約8割が樹木葬や納骨堂など永代供養型のお墓を選択肢に入れていることが分かりました。
この記事では、永代供養の意味から費用相場、選び方まで、後悔しないお墓選びのために必要な情報をわかりやすく解説します。お墓の承継者問題でお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。
この記事では、永代供養の意味から費用相場、選び方まで、後悔しないお墓選びのために必要な情報をわかりやすく解説します。お墓の承継者問題でお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。
永代供養とは何か?
永代供養とは、霊園や寺院がご遺族に代わってお墓を管理・供養する仕組みのことです。「永代」は期限を設けないという意味で、「供養」は故人の冥福を祈り弔うことを指します。
つまり、お墓の後継者が不要で、寺院等が永続的に供養してくれる新しい形のお墓といえるでしょう。従来の「○○家之墓」のように代々受け継ぐ必要がなく、自分たちの代で供養を完結させることができます。
このような供養方法が求められる背景には、現代の少子高齢化や核家族化があります。子どもがいない、または子どもがいても遠方に住んでいるなど、従来のお墓の承継が困難な家庭が増えているのが現実です。永代供養を選ぶ理由の第1位は「子どもに迷惑をかけたくない」で50.7%を占めており、多くの方が家族への負担を心配していることがわかります。
つまり、お墓の後継者が不要で、寺院等が永続的に供養してくれる新しい形のお墓といえるでしょう。従来の「○○家之墓」のように代々受け継ぐ必要がなく、自分たちの代で供養を完結させることができます。
このような供養方法が求められる背景には、現代の少子高齢化や核家族化があります。子どもがいない、または子どもがいても遠方に住んでいるなど、従来のお墓の承継が困難な家庭が増えているのが現実です。永代供養を選ぶ理由の第1位は「子どもに迷惑をかけたくない」で50.7%を占めており、多くの方が家族への負担を心配していることがわかります。
永代使用料との違い
永代供養を調べる際によく混同されるのが「永代使用料」です。名前は似ていますが、意味は全く異なります。
・永代使用料:お墓の土地の使用権に対する料金(一区画を永久に使う権利)
・永代供養料:遺骨を永代に供養・管理してもらうサービスの費用
永代使用料は土地代であり、永代供養料は供養サービス代ということになります。一般的なお墓では永代使用料を支払って土地を借り、さらに年間管理料を払い続ける必要がありますが、永代供養では基本的に最初の永代供養料のみで済むケースが多いのが特徴です。
・永代使用料:お墓の土地の使用権に対する料金(一区画を永久に使う権利)
・永代供養料:遺骨を永代に供養・管理してもらうサービスの費用
永代使用料は土地代であり、永代供養料は供養サービス代ということになります。一般的なお墓では永代使用料を支払って土地を借り、さらに年間管理料を払い続ける必要がありますが、永代供養では基本的に最初の永代供養料のみで済むケースが多いのが特徴です。
永代供養の種類と特徴
永代供養には複数の形態があり、埋葬方法や費用、供養期間などに違いがあります。主な種類とそれぞれの特徴をご紹介します。
合祀型(ごうし型)
合祀型は、複数の遺骨を一緒に埋葬・供養する最もシンプルな永代供養の形態です。
特徴
・費用が最も安価(5万〜30万円程度)
・個別の区画や墓石を持たない共同のお墓
・一度合祀すると遺骨を個別に取り出すことは不可能
・管理の手間が一切かからない
・個別の区画や墓石を持たない共同のお墓
・一度合祀すると遺骨を個別に取り出すことは不可能
・管理の手間が一切かからない
向いている人
・とにかく費用を抑えたい方
・承継者が全くいない方
・お墓参りの形式にこだわらない方
注意点:
他の方の遺骨と合同で埋葬されるため、後から改葬や分骨をしたくても遺骨を取り出せません。事前に家族でよく話し合うことが大切です。
・承継者が全くいない方
・お墓参りの形式にこだわらない方
注意点:
他の方の遺骨と合同で埋葬されるため、後から改葬や分骨をしたくても遺骨を取り出せません。事前に家族でよく話し合うことが大切です。
個別型・集合型
個別型永代供養墓は、家族ごとに個別の区画や墓石を設けて永代供養を行うタイプです。見た目は従来のお墓に近いですが、一定期間後(多くは33回忌まで)に合祀されるケースが一般的です。
個別型の特徴
・費用相場:50万〜150万円程度
・「我が家のお墓」を持ちながら永代供養できる
・期間限定で個別安置、後に合祀
集合型永代供養墓は、一つの墓碑の下に個別の骨壺スペースが区切られているタイプです。個別型と合祀型の中間的なスタイルといえます。
・「我が家のお墓」を持ちながら永代供養できる
・期間限定で個別安置、後に合祀
集合型永代供養墓は、一つの墓碑の下に個別の骨壺スペースが区切られているタイプです。個別型と合祀型の中間的なスタイルといえます。
集合型の特徴
・費用相場:20万〜60万円程度
・最初から合祀は抵抗があるが費用は抑えたい方に適している
・一定期間後に合祀される点は個別型と同様
・最初から合祀は抵抗があるが費用は抑えたい方に適している
・一定期間後に合祀される点は個別型と同様
その他の供養スタイル(樹木葬・納骨堂など)
永代供養の一種として人気が高まっているのが樹木葬と納骨堂です。
樹木葬は、シンボルツリーや花壇を墓標とするお墓で、自然志向の方に人気です。多くの樹木葬霊園では永代供養付きプランを提供しており、「自然に還りたい」という想いと「後継者不要」というニーズを両立できます。
納骨堂は、屋内施設に遺骨を安置するタイプで、天候に左右されずお参りできるのが特徴です。都市部に多く、永代供養付きの納骨堂が一般的になっています。
いずれも寺院や霊園が管理し永代に供養する点で永代供養墓の一種といえるでしょう。
樹木葬は、シンボルツリーや花壇を墓標とするお墓で、自然志向の方に人気です。多くの樹木葬霊園では永代供養付きプランを提供しており、「自然に還りたい」という想いと「後継者不要」というニーズを両立できます。
納骨堂は、屋内施設に遺骨を安置するタイプで、天候に左右されずお参りできるのが特徴です。都市部に多く、永代供養付きの納骨堂が一般的になっています。
いずれも寺院や霊園が管理し永代に供養する点で永代供養墓の一種といえるでしょう。
永代供養にかかる費用と相場
費用相場の目安
永代供養の費用相場は約10万円〜150万円と幅があります。この差が生じる理由は、埋葬する人数、供養方法、お墓の種類によって金額が大きく変わるためです。
費用の内訳
永代供養の費用は主に以下の3つで構成されます:
永代供養料(5万〜100万円)
・遺骨を永代供養してもらうための基本費用
・読経や管理費用が含まれる
・読経や管理費用が含まれる
納骨料(1万〜5万円)
・遺骨を納める際にかかる費用
・納骨法要の費用も含まれる場合が多い
・納骨法要の費用も含まれる場合が多い
刻字料(1万〜3万円)
・石板や墓誌に名前を刻む費用
・霊園によっては別途必要
・霊園によっては別途必要
年間管理料について
永代供養の大きなメリットの一つが、基本的に年間管理料が不要という点です。ただし、プランによっては以下のケースもあるため注意が必要です:
・生前契約の場合のみ年間管理料が発生
・個別安置期間中は管理料が必要
・法要ごとに別途お布施が必要
契約前に費用の内訳と、将来的に追加費用が発生する可能性について必ず確認しましょう。
・生前契約の場合のみ年間管理料が発生
・個別安置期間中は管理料が必要
・法要ごとに別途お布施が必要
契約前に費用の内訳と、将来的に追加費用が発生する可能性について必ず確認しましょう。
永代供養のメリット・デメリット
永代供養を検討する際は、良い点だけでなく注意点も理解しておくことが大切です。
永代供養の主なメリット
✓ お墓の後継者が不要
子や親族に墓守を頼む必要がなく、自分たちだけで完結できる安心感があります。
✓ お墓の維持管理の手間が省ける
寺院や霊園が掃除や供養を代行するため、遠方に住んでいてもお墓が荒れる心配がありません。
✓ 無縁墓にならない
継承者不在で墓が放置され、行政処分を受けるといった事態を避けられます。
✓ 費用を抑えられる場合が多い
一般的な墓石建立に比べ初期費用・維持費用が低めで、経済的負担が軽減されます。
✓ 宗派を問わない場合が多い
多くの永代供養墓は宗教不問で利用でき、檀家になる必要もありません。
子や親族に墓守を頼む必要がなく、自分たちだけで完結できる安心感があります。
✓ お墓の維持管理の手間が省ける
寺院や霊園が掃除や供養を代行するため、遠方に住んでいてもお墓が荒れる心配がありません。
✓ 無縁墓にならない
継承者不在で墓が放置され、行政処分を受けるといった事態を避けられます。
✓ 費用を抑えられる場合が多い
一般的な墓石建立に比べ初期費用・維持費用が低めで、経済的負担が軽減されます。
✓ 宗派を問わない場合が多い
多くの永代供養墓は宗教不問で利用でき、檀家になる必要もありません。
永代供養の主なデメリット
⚠ 遺骨を取り出せない
合祀されると遺骨が他の方と混ざるため、後から個別に分けて取り出すことはできません。
⚠ 個別に安置できる期間が限られる
個別型や集合型でも33回忌までなど期限後には合祀されるケースがほとんどです。
⚠ お墓を継承できない
永代供養墓は代々継ぐことを前提としておらず、定員も限られるため親族全員が同じ場所に入れるとは限りません。
⚠ 伝統的なお参りがしにくい場合がある
合祀墓では線香やお花を個別に供えるスペースがなく、自由度が制限される場合があります。
⚠ 親族の理解を得にくいことがある
従来のお墓と違うため、「ちゃんとしたお墓にしてあげたかった」と感じる親族もいます。
遺骨の一部を手元に残したい場合は、合祀前に分骨を検討することをおすすめします。
合祀されると遺骨が他の方と混ざるため、後から個別に分けて取り出すことはできません。
⚠ 個別に安置できる期間が限られる
個別型や集合型でも33回忌までなど期限後には合祀されるケースがほとんどです。
⚠ お墓を継承できない
永代供養墓は代々継ぐことを前提としておらず、定員も限られるため親族全員が同じ場所に入れるとは限りません。
⚠ 伝統的なお参りがしにくい場合がある
合祀墓では線香やお花を個別に供えるスペースがなく、自由度が制限される場合があります。
⚠ 親族の理解を得にくいことがある
従来のお墓と違うため、「ちゃんとしたお墓にしてあげたかった」と感じる親族もいます。
遺骨の一部を手元に残したい場合は、合祀前に分骨を検討することをおすすめします。
永代供養はこんな人におすすめ
永代供養が特に適しているのは以下のような方々です:
◆ お墓の後継者がいない、または子供に継がせたくない人
単身者や子どものいない夫婦、子どもはいても遠方在住で管理を任せたくない方に最適です。
◆ 遠方に住んでおりお墓参りや管理が難しい人
故郷を離れて暮らしている方や、高齢でお墓の維持管理が困難な方におすすめです。
◆ 経済的に墓石建立が負担な人
一般的なお墓を建てるには100万円以上かかることが多いため、費用を抑えたい方に向いています。
◆ 子供や家族にお墓の負担をかけたくない人
「墓守で苦労をかけたくない」という思いやりから永代供養を選ぶ方が増えています。
◆ 将来無縁仏になることを心配している人
管理する人がいなくなる不安を抱えている方には、永代供養が安心感を提供します。
逆に注意が必要なケース
先祖代々のお墓にこだわりたい方
家族全員が同じ場所で供養されたいと強く願う方
伝統的なお墓参りの形式を重視する方
このような場合は、一般墓の方が満足度が高いかもしれません。家族でよく話し合って決めることが大切です。
◆ お墓の後継者がいない、または子供に継がせたくない人
単身者や子どものいない夫婦、子どもはいても遠方在住で管理を任せたくない方に最適です。
◆ 遠方に住んでおりお墓参りや管理が難しい人
故郷を離れて暮らしている方や、高齢でお墓の維持管理が困難な方におすすめです。
◆ 経済的に墓石建立が負担な人
一般的なお墓を建てるには100万円以上かかることが多いため、費用を抑えたい方に向いています。
◆ 子供や家族にお墓の負担をかけたくない人
「墓守で苦労をかけたくない」という思いやりから永代供養を選ぶ方が増えています。
◆ 将来無縁仏になることを心配している人
管理する人がいなくなる不安を抱えている方には、永代供養が安心感を提供します。
逆に注意が必要なケース
先祖代々のお墓にこだわりたい方
家族全員が同じ場所で供養されたいと強く願う方
伝統的なお墓参りの形式を重視する方
このような場合は、一般墓の方が満足度が高いかもしれません。家族でよく話し合って決めることが大切です。
永代供養のお墓を選ぶポイント
後悔しない永代供養墓選びのために、以下のポイントを必ず確認しましょう。
納骨する遺骨の数を確認
永代供養墓は1霊あたりの料金設定である場合が多く、複数人分だとかえって割高になるケースもあります。まず埋葬予定の人数を明確にし、以下の点を確認してください:
・何柱まで納骨できるか(定員)
・将来追加で納骨できるか
・人数による料金体系
家族で利用する場合は、夫婦2人なのか、他の家族も含めるのかを事前に決めておきましょう。
・何柱まで納骨できるか(定員)
・将来追加で納骨できるか
・人数による料金体系
家族で利用する場合は、夫婦2人なのか、他の家族も含めるのかを事前に決めておきましょう。
埋葬方法と合祀までの期間
自分の希望する埋葬スタイルかどうかを必ず確認します:
・合祀型・集合型・個別型のどれか
・何回忌まで個別安置なのか
・最初から合祀なのか
例えば「33回忌まで個別安置、その後合祀」が一般的ですが、霊園ごとに違いがあります。合祀のタイミングは後から変更できないため、契約前に家族とも話し合っておきましょう。
・合祀型・集合型・個別型のどれか
・何回忌まで個別安置なのか
・最初から合祀なのか
例えば「33回忌まで個別安置、その後合祀」が一般的ですが、霊園ごとに違いがあります。合祀のタイミングは後から変更できないため、契約前に家族とも話し合っておきましょう。
寺院の宗派・供養の方法
永代供養墓は基本的に宗旨宗派不問が多いものの、寺院が運営する場合はその寺の宗派で供養が行われます。確認すべき点:
・宗派の制限はないか
・供養の頻度(毎日読経か、年数回の合同供養祭か)
・法要の規模や内容
特に浄土真宗では「永代供養」の概念が異なる場合があるため、不安な方は同宗派の寺院を選ぶと安心です。
・宗派の制限はないか
・供養の頻度(毎日読経か、年数回の合同供養祭か)
・法要の規模や内容
特に浄土真宗では「永代供養」の概念が異なる場合があるため、不安な方は同宗派の寺院を選ぶと安心です。
費用と維持費の有無
提示された費用に何が含まれているかを詳細に確認しましょう:
・永代供養料に納骨料や刻字料は含まれているか
・年間管理費は本当に不要か
・お布施や法要代は別途必要か
「永代供養だから基本的に追加費用なし」とされていても、生前管理料や法要ごとのお布施が別途発生することもあります。見積もりの段階で細部まで確認することが重要です。
・永代供養料に納骨料や刻字料は含まれているか
・年間管理費は本当に不要か
・お布施や法要代は別途必要か
「永代供養だから基本的に追加費用なし」とされていても、生前管理料や法要ごとのお布施が別途発生することもあります。見積もりの段階で細部まで確認することが重要です。
立地と設備の利便性
長期間お参りすることを考えて、アクセスや設備も重要な選択基準です:
・自宅からの距離・交通手段
・駐車場の有無
・バリアフリー対応
・休憩所や法要施設の設備
高齢になってもお参りしやすい環境かどうか、実際に現地を見学して確認しましょう。送迎サービスがある霊園もあります。
・自宅からの距離・交通手段
・駐車場の有無
・バリアフリー対応
・休憩所や法要施設の設備
高齢になってもお参りしやすい環境かどうか、実際に現地を見学して確認しましょう。送迎サービスがある霊園もあります。
永代供養の具体的な手続き
永代供養を利用する際の手順を、ケース別にご紹介します。
既存のお墓がある場合(改葬・墓じまい)
1.永代供養先の決定
希望エリアで永代供養墓を探し、見学・見積もりを行います。
2.親族の同意
お墓の移転について家族・親族と話し合い、同意を得ます。
3.改葬許可証の取得
現在のお墓がある市町村役場で改葬許可申請を行います。
4.遺骨の取り出し
石材店に依頼して墓石を撤去し、遺骨を取り出します。
5.新しい永代供養先へ納骨
納骨法要を執り行い、永代供養を開始します。
希望エリアで永代供養墓を探し、見学・見積もりを行います。
2.親族の同意
お墓の移転について家族・親族と話し合い、同意を得ます。
3.改葬許可証の取得
現在のお墓がある市町村役場で改葬許可申請を行います。
4.遺骨の取り出し
石材店に依頼して墓石を撤去し、遺骨を取り出します。
5.新しい永代供養先へ納骨
納骨法要を執り行い、永代供養を開始します。
新規に利用する場合
1.情報収集
インターネットや資料請求で希望に合う霊園・寺院を探します。
2.現地見学
実際に霊園を訪れ、住職や担当者に相談します。
3.契約手続き
プランを決定し、永代供養料等を支払います。生前契約も可能です。
4.納骨法要
日程を調整し、僧侶による読経のもと納骨を行います。
インターネットや資料請求で希望に合う霊園・寺院を探します。
2.現地見学
実際に霊園を訪れ、住職や担当者に相談します。
3.契約手続き
プランを決定し、永代供養料等を支払います。生前契約も可能です。
4.納骨法要
日程を調整し、僧侶による読経のもと納骨を行います。
生前契約について
多くの寺院・霊園では生前申込みが可能です。生前契約のメリット:
・自分の意思で供養方法を決められる
・家族の負担を軽減できる
・費用を事前に支払えば家族が慌てる必要がない
気になる永代供養墓があれば、生前予約について問い合わせてみましょう。
・自分の意思で供養方法を決められる
・家族の負担を軽減できる
・費用を事前に支払えば家族が慌てる必要がない
気になる永代供養墓があれば、生前予約について問い合わせてみましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 永代供養と納骨堂の違いは?
A1. 納骨堂は屋内施設に遺骨を安置する「お墓の形態」で、永代供養は遺族の代わりに寺院や霊園がお墓を管理・供養してくれる「サービス内容」のことです。納骨堂にも永代供養付きのものがあり、**納骨堂は"入れ物"、永代供養は"供養の仕組み"**と考えるとよいでしょう。
Q2. 永代供養にお布施は必要ですか?
A2. 一般的には契約時に支払う永代供養料にお布施(読経などへの謝礼)が含まれていることが多いです。ただし契約内容によるため、含まれていない場合は納骨法要の際に数万円程度のお布施を渡すのがマナーです。事前に寺院へ確認しておきましょう。
Q3. 永代供養料を払う時のマナーはありますか?
A3. 当日現金で支払う場合、基本的にはお布施と同様のマナーで渡します。白無地の封筒に「永代供養料」と表書きし、自分の氏名を記入します。水引は不要です。銀行振込や口座引落の場合は指示に従いましょう。
Q4. 永代供養に宗派は関係ありますか?
A4. 基本的に宗旨・宗派を問わず誰でも利用できます。多くの永代供養墓は宗教不問ですが、寺院によっては檀家のみ受け入れなど条件がある場合もあります。また供養は管理する寺院の宗派の形式で行われるため、自分の宗派にこだわりがある場合は事前確認が必要です。
Q5. 浄土真宗では永代供養できないって本当ですか?
A5. 浄土真宗では「故人はすぐ成仏する」という考えから本来「永代供養」の概念がないと言われます。ただ、実際には浄土真宗のお寺でも永代供養墓を利用することは可能です。浄土真宗の場合、本山に納骨する方法や、宗派不問の霊園を利用する方法があります。宗派が心配な場合はその宗派の寺院が行う永代供養を選ぶと安心です。
Q6. 子どもがいても永代供養を選んでいいのでしょうか?
A6. はい、子ども(後継者)がいても**「子供に迷惑をかけたくない」という理由で永代供養を選ぶ方は多いです**。お墓の承継という負担を子世代に残さず、自分達の代で供養を完結させたいと考える家庭も増えています。事前にご家族とよく話し合い、皆が納得した上で決めるとよいでしょう。
Q7. 永代供養墓でもお墓参りはできますか?
A7. できます。永代供養墓でも多くは合同の慰霊碑や納骨壇の前で自由にお参り可能です。ただし個別の墓石がないため、線香や花を供える場所が限定されている場合があります。霊園によっては共同の祭壇を用意しているので、事前にお参り方法を確認すると安心です。
まとめ
永代供養は、現代社会のニーズに応える新しい供養の形です。後継者不要で費用も抑えられるため、「子どもに迷惑をかけたくない」「将来の不安を解消したい」という方には最適な選択肢といえるでしょう。
一方で、遺骨を取り出せない、個別安置期間に限りがあるなどの注意点もあります。メリット・デメリットを十分に理解し、ご家族とよく相談した上で決めることが大切です。
永代供養はあなたの状況次第でとても有効な選択肢になります。本記事を参考に、ぜひ後悔のない供養方法を選んでください。心配事がある場合は、複数の霊園を見学し、納得いくまで相談することをおすすめします。
一方で、遺骨を取り出せない、個別安置期間に限りがあるなどの注意点もあります。メリット・デメリットを十分に理解し、ご家族とよく相談した上で決めることが大切です。
永代供養はあなたの状況次第でとても有効な選択肢になります。本記事を参考に、ぜひ後悔のない供養方法を選んでください。心配事がある場合は、複数の霊園を見学し、納得いくまで相談することをおすすめします。